セミナー
 川崎市立川崎病院
 桑野隆司さん
|
◆終了 第52回催事:美産会世話人 桑野隆司さん主宰研究会『いま病院設計が抱える課題とアートの導入』 1月19日(土) パブリックアート研究所図書室。日本は今、少子高齢化、経済の停滞・価格低廉化・省エネ化、その中で進む日本の文化熟成化など、従来にない状況変化に遭遇中で、病院設計の世界もそれらの変化に合わせたハードとソフトの設計が要求されている。美産会世話人、桑野隆司氏は、日本の医療施設設計界のリーダーの一人。 長年、設計・監理・コンサルティングの仕事を通じて日本や外国の病院施設向上に尽くすと共に、医療福祉アートの導入も早い段階から取り組む。日本の医療福祉が厳しい転換期を迎えている中で、設計分野の専門家は、社会の要求にどう応えようとしているのか。その現況を同氏の代表作「川崎市立川崎病院」や、現在取り組み中のプロジェクトを事例に、アート導入の是非をも含めて語る。 期日平成20年1月19日(土)16:00~18:30、参加人数 15名。参加希望者はNews.52で詳細を確認し、News内の参加申込頁に記入Fax等で参加申込を送信。 |

|
◆終了 第49回催事:9月20日(木)夕:地域美産会、“心の美産研究会Ⅲ”『新渡戸「武士道」7つの要点を参考に、日本と諸外国の「人としの礼儀」を探り 話し合う』がPA研究所杉村荘吉の司会で開催。
今回の研究会では、「公徳心」の基盤となる「人としての礼儀(Human Manner)」について、日本と外国における相似と相違を、新渡戸・武士道を構成する8つの要素などを切り口に紐解く予定。それらが家庭や学校、職場、公共の場や外国などで、一寸した場面に遭遇した際、人の心を落ち着かせて適確な行動をとれる基になる、次代の日本の「人としての礼儀」/「公徳心」づくりに必要な何かを、参加者と一緒に探る。 |
 会場瑞泉寺(堅固な堡塁が
寺院を囲む) 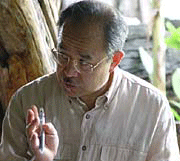 ファシリテータ
長谷川富山大教授 |
◆終了 第48回催事:第2部 『パブリックアートフォーラム IN いなみ』「南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ」2007(8/18~9/1)併催事業‥「南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ」では、木彫刻を屋外で制作し、それをパブリックアートとして屋外設置してきた。日本には「木造」の建築物はあっても木彫刻を屋外設置するというケースは多くない。パブリックアートフォーラムをとおして、木彫刻の屋外設置や伝統産業の活性化などの視点から、パブリックアートとまちづくりについて意見交換をする。 8月26日(日)午後2:00~4:00 テーマ 「木彫刻・まちづくり・パブリックアート」 総合司会 橋本 完(建築家/アトリエまほろ主宰 大阪) 第1部 トークセッション‥杉村荘吉(PAフォーラム地域美産会代表 東京) 第2部 パネルセッション‥ 藤嶋俊会(美術評論家・元神奈川芸術文化財団ギャラリー課長)、 伊豆井秀一(埼玉県立近代美術館学芸主幹)、山岡義典(法政大学教授/日本NPOセンター副代表理事)、藤崎秀胤(仏師/チェコとオーストリアの木彫刻キャンプ参加者 井波) ファシリテータ 長谷川総一郎(富山大学芸術文化学部教授) 会場/井波別院 瑞泉寺 太子堂、富山県南砺市井波3050 TEL 0763-82-0004 入場無料 一般参加大歓迎!! ■ 主催 パブリックアートフォーラムINいなみ実行委員会 その他 当日は「全国木彫刻サミットin井波」で各産地の木彫刻を実演中(瑞泉寺太子堂外縁) |
 概括報告説明会
 感謝午餐会
|
◆終了 第45回催事:「年度末パーティ:今期報告/来期概括会と感謝午餐会」、平成19年3月10日(土)10:00~14:30、PA研究所・ウラク青山。3月は第4年度活動の最終月に当ることから、卒業期と学校休み期に入る後半を避けて早目の10日(土)に、1. 午前中、今期の活動内容を収支推移も含めての報告会、4月から始まる第5年度活動の概括説明会、2. 場所を変えて、45回に達した美産会活動へのご支援感謝と参加者同士の交歓を目的に、「感謝午餐会」を外苑前「ウラク青山」で開催。午前の会では藤島さんによる、同氏企画案内美産会の過去とこれからを概括する話も興味深い内容だった。 期日:2月10日(土)10:00~14:30、参加人数≒ 25名。参加希望者はNews.45で詳細を確認し、News内の参加申込頁に記入Fax等で参加申込を送信。 |
 |
◆終了 第42回催事:杉村荘吉企画、心の美産研究会Ⅱ『新渡戸「武士道」のエッセンス/今なぜ武士道か』12月16日(土)午後 PA研究所日本特有の自然環境は、そこに暮らす人々に日本ならではの感性や倫理感を育み、それらが他国に無い美しい公徳心を育んだが、戦後60年それは軍国主義に結び付くもの、自由主義に反するものとして忌避された結果が、今頻繁に発生する行政や教育現場の乱れ個人生活の乱れに繋がった。 去る8月開催の心の美産研究会Ⅰ「新渡戸稲造『武士道』読書会」で分かったことは、「このような乱れを正す為に、次代の日本に見合う公徳心をもう一度取り戻したい、その為「新渡戸稲造『武士道』について知りたい」とする参加者たちの想い。 “新しい時代に見合う日本のPublic Manner探し”がこの研究会の新テーマ。今回はその序編と位置付けて、PA研究所/地域美産会代表の杉村荘吉が新渡戸『武士道』の真髄・エッセンスを、美産会々員で日本史愛好家、田中啓介が「武士道ブーム四つの波」「女性と武士道」等を語った後、参加者同士が自由な意見を交換する。 期日:12月16日(土)14:00~16:00、参加人数 25名。参加希望者はNews.42で詳細を確認し、News内の参加申込頁に記入Fax等で参加申込を送信。 |
 コニシ(旧小西儀助商店)
 「適塾」公園
|
◆終了 第41回催事:大阪の美産会員 橋本 完さんの大阪美産研究会Ⅰ、『日本の近代医薬発祥の地・大阪に薬種問屋の歴史・文化美産を訪ねて、大阪再生の魅力づくりを考える』 11月22日(水)夕 大阪市中央公会堂
2階 第6会議室。
|
 鶴岡八幡宮
 研究会風景
 白拍子の舞
|
◆終了 第39回催事:鎌倉美産研究・探訪会-Ⅳ
|
 撮影、PA研究所
|
◆終了 第38回特別催事:PA研究所代表 杉村荘吉の企画構成、新渡戸稲造の「武士道」 英語版読書会、パブリックアート研究所: 8月23日(水)18時~20時、参加者13名。
日本の人々が暮らしの歴史を通して練り上げた自律自尊の精神を、心の美産として捉え、その普遍性と国際性を新渡戸稲造の「武士道」英語版に尋ねる。当日はシンガポール大使館一等書記官を含む、一般市民から専門家まで13名が参加。本の概要、新渡戸の経歴と当時の日本を巡る国際環境等を、杉村と戦後日本の海外事業開拓者で財界の国際リスクマネジメントアドバイザー、江川淑夫の解説をまじえて学習し、自由な意見を交換。次回からは、新渡戸「武士道」以外からも「日本道徳」の源を探り、次の時代に必要な日本の道徳づくり研究会への転進が要望された。 |
 海外研究者交流研究会
 「ミューザ川崎」のアートワーク
|
◆終了 第37回特別催事:●日本のパブリックアート、その変遷と意義・役割 『日英2名の研究者が、日本のパブリックアートの変遷、その意義・役割を語り、事例を川崎に尋ねる』 研究会(東京PA研究所): 7月19日(水)夕日本のパブリックアートは、1960年代に活動を開始して以来40余年、時々の状況と時勢に従って内容やその意義に変化を続けている。そして明日のパブリックアートはどうなるのか。 今回の研究会は、神奈川芸術文化財団で長年パブリックアート関連の調査研究・催事企画・評論活動を続けてきた当会の世話人、藤島俊会さんと、昨年英国 Leeds大学にPhD論文“The culture and Practice of Public Art in Japan”を提出し、博士学位を取得した英国人Elizabeth H. Norman さんのお二人が、夫々なりに観察した日本のパブリックアートの変遷・その意義などについて辛口コメント?を含めて語る予定です。 この特別催事の特徴は、久しぶりに来日するNormanさんのご協力もあって、日本におけるパブリックアートの意義・役割・変遷を、東西二つの視点から学べる点にあり、アートを愛する市民・学生は勿論、「パブリックアート」自身や「まちづくりにおけるアートの役割」に高い関心を持つ人々には、垂涎の研究会で、藤島俊会さんの案内と解説で川崎を訪ねて、最近JR川崎駅西口に完成した「ミューザ川崎」のアートワークたちと、20年前の同駅東口開発時につくられたパブリックアートたち等を比較検証する研究会と探訪会「ここをクリック」双方への参加がお勧めです。 期日:7月19日(水)18:00~20:30(予定)、参加人数 20名。参加費(会員/学生/地元市民 1,500円、他)。参加希望者は、News.No.36で詳細確認し、News内の参加申込頁に記入、Fax送信等で申込。News 37入手先は地域美産会事務局、Tel: 03-3407-9132 Fax: 03-3407-5247、http://bisan.seesaa.net )。 |
 夕映えのモエレ山公園
 60622研究会八代さんの解説
|
◆終了 第36回催事:●札幌の最新美産研究会『最近完成したアートたちを訪ねて、サッポロの都市と観光の新しい魅力を探る』研究会(東京): 6月22日(木)札幌高等専門学校の環境デザイン科教授で当会アドバイザー/会員、後藤元一さんの企画と人脈で、イサム・ノグチ最後の企画・デザインプランを具現化した札幌市モエレ沼公園と、札幌の文化都市づくりの拠点・札幌芸術の森などに、都市と観光の新しい魅力を探る。 評論家の浅田彰は『この夏行くとしたら、やっぱり札幌郊外のモエレ沼公園でしょう。モエレ沼のゴミ捨て場を公園に変えよと、イサム・ノグチが88年に亡くなるまで頑張ってマスタープランをつくった。それをもとに、彼の志を継ぐ人たちが、札幌市の整備事業として189へクタールに及ぶ公園を、2005年までかかって完成させた。公園そのものが彫刻だっていうコンセプトでさすがに壮大だよ』と語った。モエレ沼公園は、新たなサッポロ文化・観光イメージを担うシンボル。 研究会ではモエレ沼公園研究家第一人者、八代克彦さん(ものつくり大学助教授)が「モエレ沼公園に託したイサム。ノグチのメッセージ」というテーマで、その意義・特徴魅力などを解説。 期日:6月22日(木)18:00~20:00、参加人数 20名。参加費:会員 1,000円 一般 2,000円 。参加希望者は、News.No.36( 美産会事務局Tel: 03-3407-9132 Fax: 03-345247、http://bisan.seesaa.net 連絡で入手)で詳細確認、同News内の参加申込頁に記入、Fax送信等で申込み。 |
 杉村代表の田中講師紹介
|
◆終了 第35回催事:●京都の美産研究会‐2『京都の食文化の源を錦市場に尋ね、錦が育んだ京料理の粋を秦家で味わう』、平成18年5月17日(水)PA研究所、18~20時。昨年大好評の「京都美産会‐1」に引き続き「京都美産研究-2」開催。今回は、美産会員で寺社修復の建築設計家・田中 哲さんが企画。 京都の錦小路市場は室町中期頃に寺院等への食材供給を担って発生。現在は道幅3.2m、長さ390m、店舗数147店の横長市場に成長。マチ(京都)とイナカ(産地)との歴史的な関係、その関係が培った縁で織り上げた役割が、京・錦市場の存立基盤。 今回の美産研究会は、京文化の洗練化に大きな役割を担ってきた寺院の「炉」と「錦市場」との繋がりを、東京で学んだ後、20日(土)に京都でその実際を見て肌で理解するところが特徴。 期日:5月17日(土)18:00~20:00、参加人数 20名。参加費:会員 1,000円 一般 2,000円 |
 大宮氷川神社
|
◆終了 第33回催事:● 伊豆井秀一世話人の企画案内による、さいたま美産研究・探訪シリーズ-4「さいたま新都心、そして氷川神社周辺の美産」;研究会:平成18年3月15日(水)PA研究所、18~20時。3月18日(土)開催する、さいたま新都心周辺の「明日のさいたま」と、永い歴史をかけて「昨日までのさいたまづくり」を担った旧大宮市の発展の礎(いしずえ)、武蔵(むさしの)国造(くにのみやつこ)の鎮守として大和朝廷成立以前から在ると言われる武蔵一宮、氷川神社とその周辺の文化的美産の散策のための事前勉強会。 審美性、歴史性を体感出雲大社につながる武蔵一宮、氷川神社誕生の古い歴史と、大宮市が埼玉県庁所在地にならなかったとされる政治的背景などを、伊豆井秀一世話人(埼玉県立近代美術館学芸主幹)解説。 詳細資料請求と参加申し込み:パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132、Fax 03-3407-5247研究会。 |
 地域美産研究会風景
|
◆終了 第32回催事:●特別企画『地域美産会過去3年間の活動を祝して日本の都市設計のリーダー加藤 源さんの特別講演会、来期活動企画案の発表、交歓パーティ』;平成18年2月18日(土) 10:00~16:00特別講演会:当会会員で、日本を代表する都市計画・設計家として長年全国各地の都市づくりにかかわってきた加藤源さんが、「人を魅きつける都市空間と地域美産」と題して、現在開発中の東京豊洲の大規模都市再開発事業を含めて講演。豊かな知性に加えて易しい言葉を選んで話す口調は、上質な煎茶が醸す渋さと深さを備えた内容を期待できる。加藤源;日本都市総合研究所所長。1964年東大(建築)卒、1997年ハーバード大大学院(都市デザイン)卒、工学博士。現在、東京湾岸豊洲、石川島播磨工業造船所跡地再開発事業で新街区づくりに、造船所が残した産業美産などをちりばめる事業を推進中。参加者19名。 来期活動企画案発表会:美産会員、アドバイザー、世話人等関係者の尽力で、第4年度の催事活動案作成中。会員有志による新規企画案が充実し、札幌・京都・大阪など遠出会や、催事への日本・外国学生招待プロジェクトなども実現出来そう。これらの活動案につき会員意見を聴取し上で、最終案を作成。参加者19名。 年度末交歓パーティ:昼食を兼ねて、会員有志の運営協力による交歓パーティです。表参道「Jazz Bird」で開催。参加者11名。 詳細資料請求と参加申し込み:パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132、Fax 03-3407-5247研究会 |
 PA研究所図書室
|
◆終了 第31回催事:●特別企画『米国人環境美学研究家、バーバラ・サンドリッセ女史とのフリートーク+ランチ会』 PA研究所図書室+魚料理「やんも」; 12月8日(木)10:30~19:00社や鳥居、桜や稲田等、日本の自然が織りなす日本ならでは環境美産たちの研究家バーバラ・サンドリッセさんが、一年ぶりに東京に立寄る機会を活かした特別催事。 緊急連絡のため小人数の会となったが、その分各参加者はサンドリリッセさんと充分懇談ができ、特に当日そのために富山から参加した長谷川会員をはじめ、愛甲会員のご子息(高校生)飛び入り参加も含めて、午前中のトーク会、「やんも」でのランチ会、午後のカフェーでの続き会など、19時過ぎまで交流が弾む。会話は英語主体で行なわれた。 |
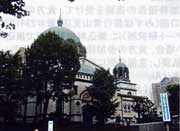 駿河台ニコライ堂
|
◆終了 第30回催事:●地域美産探訪/研究会「神田界隈、湯島聖堂から古書の街・学生の街を歩く」;研究会 平成17年12月14日(水)、PA研究所図書室美術評論家で地域美産研究・探訪会世話人、藤嶋俊會さんが解説・案内する「神田界隈の美産たち研究・探訪会」。神田川を挟んで湯島聖堂から神田明神、万世橋を渡って、神田駿河台から神田神保町にかけて、江戸から明治、大正、昭和、現在と、発展と変化を繰り返す神田界隈の文化的な側面を歩きなが見て歩く。江戸の名残を残す湯島聖堂と神田神社。駿河台で明治の建築ニコライ堂、由緒ある大学や病院、有名な出版社や個性豊かな古書店、大正時代の雰囲気を感じさせる文化学院、アールデコ様式の建築山の上ホテル、靖国通り沿いの古書店街。探訪会終了後の交歓会は神保町界隈の銘舗で、忘年会を兼ねて開催。 期日:12月14日(水)18:00~19:30、参加人数 20名。参加費:会員 1,000円 一般 2,000円参加希望者は、地域美産探訪/研究会News.No.28(sugi-p@publicart.co.jpへ連絡入手)で詳細を確認の上、同News内の参加申込み頁に記入の上、Fax送信で参加申込み。 |
 朝夷奈切通し、PA研撮影
|
◆終了 第29回催事:●地域美産研究・探訪会「鎌倉の美産研究・探訪会」シリーズⅢ、『晩秋の鎌倉に、中世名残の寺社と切通しを訊ねる』; 研究会 平成17年11月16日(水)、PA研究所図書室当会の会員で、鎌倉に生まれ、鎌倉で育ち、鎌倉の街づくりに銀行退職後の人生を燃やして、鎌倉の街と文化の深化に尽くす岡林 馨さん自身が企画・案内する「鎌倉の美産研究・探訪会シリーズそのⅢ」で、今回は、1)幕府の開府以前の古い鎌倉の地を物語る古寺・古社めぐり、2)東西北の三方向を険しい丘陵とその上に幾重に繁茂する常緑樹林を、外敵侵入を防衛する無比の手段として用いた鎌倉幕府が、他所との交通のために丘陵を掘削して設けた七箇所の「切通し」。その代表的な一つ「朝夷奈切通し」を訪ねる企画です。 事前に資料を学ぶ研究会(10・16水)と、探訪会(10・19土)後に開催の交歓会(昭和初期開店のレトロな仏風洋食老舗「小町園」で昔懐かしいオーソドックスな洋食を味わう)にも参加して、鎌倉の豊な歴史と文化を堪能下さい。 期日:研究会は10月16日(水)18:00~19:30、探訪会は10月19日(土)10:30~16:30、雨天の時 雨天実施。参加人数 25名。参加費:研究会の場合 会員 1,000円 一般 2,000円 参加希望者は、地域美産探訪/研究会News.No.28(sugi-p@publicart.co.jpへ連絡入手)で詳細を確認の上、同News内の参加申込み頁に記入の上、Fax送信で参加申込み。 |
 地域美産研究会風景
|
◆終了 第21催事、第11回研究会:平成17年3月20日(日)、パブリックアート研究所図書室「地域美産会2年間の活動を記念して、田村 明さん(名誉会員)と角坂 裕さん(世話人)の記念講演会と、会員有志の企画・運営による記念交歓パーティ」 記念講演会(第11回研究会):時間場所;14:00~17:15 パブリックアート研究所図書室。 記念交歓パーティ(第1回):18:00~20:00、表参道沿いレスラン「ベルーガ」。「ベルーガ」は、内装が本格的アールデコの設え(しつら)で有名。房総の自家農場直産の有機栽培食材による特別料理提供。川越、房総佐貫、原宿表参道探訪会などで参加者に熱い想いを語った地元の名士たちも参加。
|
 川越市新河岸
|
◆終了 第20回催事、第10回研究会:平成17年2月23日(水)、パブリックアート研究所図書室埼玉県立近代美術館学芸主幹伊豆井秀一さんの企画と案内で『江戸文化に根ざす、川越市とっておきの美産たち‥そのⅡ<江戸期に建てられた歴史的建造物を訪ねる>研究会』 詳細情報は、探訪会頁(クリック)で。 |
 羽田無縁堂
|
◆終了 第19回催事、第9回研究会:平成17年1月27日(木)、パブリックアート研究所図書室素朴な社探訪家、角坂 裕さんが案内する、『私が愛する多摩川水系の素朴な社(やしろ)と美産たち‥そのⅢ』<多摩川の河口、羽田猟師町界隈の社と美産> 結果は「催事の記録」頁(クリック)で。 |
 「造景」No21より
 大地の芸術祭資料より
 研究会風景
|
◆終了 第18回催事、第8回研究会:平成16年12月11日(木)15:00~19:30美術評論家で当会世話人、藤嶋俊会さん企画による 18 回目の催事は、当会世話人の一人藤嶋俊会さんが、パブリックアート研究家の立場から、過去数年の間新潟県十日町市を含む中越豪雪地帯、妻有地域の地域おこしに現代アートを活用する北川フラム提案のアートプロジェクト、第2回妻有トリエンナーレの成果を現地に訪ねて調査した結果を、スライドを交えて報告し、現実の地域社会づくりに参加したアートの可能性とその限界を当日の参加者と語りあうという、パブリックアート愛好家にとって垂涎の企画です。 愛好家でない人々にとっては、農林業の厳しい生活に生きる豪雪地帯の人々が、自分たちの生活とはまったく縁がなかった現代アートとどう付き合っているかを知る、大変興味深い企画となります。この地域は今回の中越地震の被害地域とも重なり、現地に設置されたパブリックアートにも被害が及んでいるようで、その状況も聞くことができそうです。 研究会の後は忘年会です。今年度催事への参加体験を肴に参加者一同で好き勝手なことを喋り合って今年のウサを吹き飛ばし、一年を納めましょう。 北川フラム:アートディレクター、アートフロントギャラリー(東京代官山)代表。アートが公共の場づくりに発揮する力を、アートディレクターとして代官山、ファーレ立川、越後妻有地域プロジェクトなどで実践中。 越後妻有アートネックレス整備事業:今年知事を辞した平山征夫新潟県知事が、知事就任直後に提唱した「ニュウーにいがた里創プラン」を1996年にパブリックアートの効用を導入した「越後妻有アートネックレス整備構想」として纏め、1997年北川フラムを総合コーディネーターに任命して、妻有アートトリエンナーレ等の地域おこしアートプロジェクトが始まる。 藤嶋俊会:今年3月まで神奈川県芸術文化財団で現代アートのキュレーターとして活躍。同時にパブリックアートの研究・評論家として著名。現在美術評論と大学講義等に活動を広げる。 研究会:時間場所;15:00~17:00 パブリックアート研究所図書室(表参道駅A1口上る) 参加申込と受付:下記申込手続きに従って。参加費:会員1,500円 一般3,000円 忘年会:この一年間美産会活動で知り合った仲間たちが、世話人を交えて好き勝手なことを喋りあい、今年のウサを吹き飛ばしながら一年を納める。 |
 東京表参道
 地域の護り社
 有名ブランド店
|
◆終了 ●第16回催事、第6回研究会:平成16年10月14日(木)17~19時『原宿表参道に古き美産(鳥居や社等)を訪ねて、新しきを知る』探訪会の勉強会 僅か50数年前の原宿表参道は、明治神宮とその横に広がる米国駐留軍キャンプに通じる、人通りの少ない閑静な欅並通りだった。 だが現在は、表通りだけでも日本や外国を代表する有名ブランド店が50以上も進出し、この街を訪ねる人々の数は年間数百万人を越えるエレガントな街に大変貌。豊かに茂る大けやき並木がつくり出す優雅でさわやかなモール(緑道)と横路には、ファッションの最先端店がつくりだす多彩な高品質商品とサービスに惹かれて、国内、アジア、欧米の各国から、ヤングからシニアまで、個人から家族連れまで、あらゆる階層の人々がやってくるトレンディな街に大変身。 20 余年前から、地域の商店街街づくり計画に係わる間、この街の歴史や文化の重層性も学んできたPA研究所、杉村荘吉さんが、原宿表参道の美産探訪会‥そのⅠ (概観編)の開催に先がけて企画した事前勉強会。 原宿表参道の成り立ちの源を、鎌倉時代以前まで遡って訊ねながら、今この街に現れた多彩な美産たちの価値と審美性の源を探りながら、参加者と一緒に明日の街の魅了づくりに必要な要素を考えます。*原宿表参道の美産探訪会‥そのⅠ(概観編)の詳細は「ここをクリック」 期日場所;平成16年10月14日(木)17~19時。パブリックアート研究所図書室(表参道駅A1口上がる) 講師:パブリックアート研究所代表 杉村荘吉 参加人数:15名 参加費:会員1,000円 一般2,500円 但し10月16日(土)探訪会参加者は無料。 申込手続:1. 「入会.催事申込み(ここをクリック)」頁の所定記入事項欄に書込み送信か、案内ちらし(入手希望者はsugi-p@publicart.co.jp へ)参加申込欄記入でパブリックアート研究所内の地域美産探訪会事務局へ送付。2. 事務局から貴方の参加枠確保の連絡を受けて、指定振込口座(みずほ銀行青山支店、普#2341030、(株)パブリックアート研究所)に参加費を振込料自己負担で払込む。3. 払込みない場合は参加権喪失。振込済み料金払戻し:主催者側の瑕疵以外は払戻不可。交歓会:研究会終了後、自由参加(≒3千円) |
 佐貫美産研究会
 JR内房線佐貫町駅
 宮 醤油店
|
◆終了 ●第13回催事、第5回研究会:平成16年5月18日(火):15時~17時;「パブリックアートと地域美産‥房総佐貫に江戸から続く醤油銘蔵と旧ご城下跡を訪ねて、地域の美産を味わい街おこしの可能性を考える」 パブリックアート研究所図書室 JR内房線の佐貫駅は、東京駅から1時間余り特急に乗ると着く全くの田舎駅で、そこから佐貫の中心地区へ通じる道も日本のどこにでもある動きが止まった田舎の風景。 千葉県房総半島は、黒潮による気候の暖かさ、魚貝類の豊かさ、海上通行の容易さなどに恵まれて、縄文の昔から人々が豊かに暮らしてきた所です。そして今回訪ねる佐貫の町は、倭名類聚抄(930年)に上総国天羽郡「讃岐郷」として古くから登場する町で、鎌倉時代以後、北條、里見、徳川傘下の武将たちが代々「佐貫」の地に城を構えたことから繁栄を保ってきた土地ですが、明治の廃藩置県以後は内房における中心核の一つとしての地位を失い、年々縮小の道を辿って今日のような何もない田舎町に変貌しました。 だが一見何もない田舎町も少し立ち入って目を凝らして眺めると、人々が地域の歴史の中で造り残してきた魅力あるモノたちが見えてきます。例えば杉村荘吉が提唱する”息をしている美産たち”=6代にわたって営々と伝えてきた家業がその営みなの中で創り伝えてきた魅力溢れる美産たち‥天保五年(1834)創業の「『タマサ醤油』伊勢正、宮商店が今に伝える美産たちです。加えて佐貫の歴史が遺した旧城下町、亀城址、城主の墓所などの歴史的な地域の社会遺産。 この研究会は、パブリックアート研究所代表、杉村荘吉が、佐貫の町の事例をもとに、「パブリックアートと地域美産との関係」、「地域の美産探訪と、まちおこしの可能性」について述べながら、社会のために働くアート、パブリックアートのまちおこしにおける役割を、参加者の皆さんと一緒に勉強する会です。 講師:パブリックアート研究所代表 杉村荘吉 |