ニュース
 新潟・越後妻有の パブリックアート |
11月7日(土):日本のパブリックアート、創作時代から観賞時代へ移行?
|
 文化資源学会誌 |
11月1日(土):文化資源学会第14回研究会開催。
|
 ランドマークプラザ内 巨大な吹き抜け空間設置の 飛込み台 |
11月15日(土):地域美産研究会の57回催事は
|
 登録有形文化財の割烹旅館 「二葉」 |
10月18日(土):地域美産研究会の56回催事は
|
 ロバート・インディアナ 「LOVE」 |
10月1日:フリーマガジン「URBAN LIFE METRO」10月号
|
 美しが丘第二公園 親子のカバの像 |
9月30日~10月13日:3年に1度開催の
|
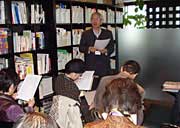 PA研究会風景
|
7月26日(土):「復活、パブリックアート」Ⅴ、地域美産研究会の55回催事は「再開、パブリックアート研究会」。地域美産研究会は、パブリックアートが再び社会的役割を回復しつつある状況に合せて、「再開、パブリックアート研究会」を開催。第一部は、新宿副都心街区に作られたパブリックアートの二大ビッグプロジェクト、新都庁舎と新宿アイランドのそれらを、パブリックアート研究者、柴田葵さんの案内と解説で現場に訪ねる「探訪会」。第二部は講演・研究報告会で、仮称{日本のパブリックアートの歩みと今」を美術評論家の藤島俊会さんが、仮称「新宿副都心のパブリックアート」を大学院博士課程在籍中の柴田 葵さんと、ベテラン新人研究者2名による講演・報告会。 詳細情報:第一部探訪会、第二部研究会‥「ここをクリック」 |
 東京青山こどもの城太朗の
「こどもの樹」 |
7月10日(木):「復活、パブリックアート」Ⅳ、岡本太朗のパブリックアートを国道246号沿街区(東京青山から川崎市まで)に配する「TAROの道」構想づくり。都心から川崎市に続く国道246号線を、その界隈に点在する岡本太朗ゆかりのパブリックアート作品や美術館等のアートで味付けをして、地域の街づくりを促したいとする「TAROの道」構想をNPO「明日の神話保全継承機構」が提案。同機構は、岡本太朗の生誕百年に当たる平成23年までに、地下鉄副都心線渋谷駅とJR渋谷駅を結ぶ、渋谷マークシティー内の連絡通路に取り付けらる岡本太朗の巨大壁面作品「明日の神話」の保全・維持を担う目的で設立されたNPO。その横を通る青山から渋谷を抜け川崎に貫ける国道246号沿線界隈に、岡本太郎作品を集めた美術館(港区と川崎市)やパブリックアート作品(青山こどもの城の「子どもの樹」、母岡本かの子のために制作した文学碑(川崎市高津区)などが点在していることから、芸術文化を街づくりに活かす「TAROの道」づくりを構想。 詳細/問合せ:明日の神話保全継承機構:http://www.salf.or.jp/tarotoshibuya/index.html |
 新宿3丁目駅、山本容子の
PA作品 |
7月1日(火):「復活、パブリックアート」Ⅲ、東京メトロ 副都心線の駅夫々に見合うパブリックアートたち登場。東京メトロは、6月14日(土)に開業した埼玉県和光市駅から渋谷駅を結ぶ副都心線のうち、渋谷・池袋間8駅に、14点の壁面主体のパブリックアートを導入。アメニティ機能の充実と地域文化情報の発信基地として「駅を楽しみ地域を楽しむ駅」をコンセプトに駅ごとに異なるデザインモチーフを採用して、例えば雑司ヶ谷駅では、ケヤキ並木をイメージするグラフィック処理を施したベンチ。新宿3丁目駅では山本容子制作の、壁面パブリックアート“Hop,Step‥”が、伊勢丹のショッピングバックとコーディネイトするなど、地域の新しい芸術・文化の創造を図っている。 詳細/問合せ:東京地下鉄株式会社 : http://www.tokyometro.jp/fukutoshin/ |
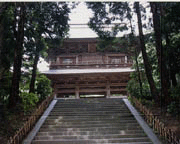 北鎌倉 円覚寺
|
6月21日(土):地域美産研究会 第54回特別企画催事『北鎌倉心(こころ)塾』を北鎌倉円覚寺/東慶寺山内で開催。 心の美産研究会シリーズそのⅣ『北鎌倉心塾』と題し、日本の公徳心(Public Manner)発祥の源を北鎌倉に尋ねる企画。 詳細は、関連頁(活動→セミナー / 探訪会)又は同会制作の「News54」で。 |
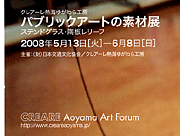 素材展
|
「パブリックアートの素材展」5月13日(火)~6月8日(日)東京外苑前で。(財)日本交通文化協会はこのほど東京外苑前に“クレアーレ青山アートフォーラム スタジオ1.2 をオープン。それを記念して企画展「パブリックアートの素材展」を開催。ステンドグラス、陶板レリーフなど、駅のコンコースを彩る鉄道向けパブリックアート作品用素材を展示紹介(11時~20時)。 「CREARE Aoyama Art Forum」港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER, 地外苑前駅徒歩2分。 |
 平成20年8月開催いなみPAフォーラム
|
4月14日(月):地域美産研究会の第6年度の活動事業、スタート平成14年(2002年)12月始まった地域美産研究会の活動は、この4月から第6年度に入り下記の特徴を基に実施の予定。 1 質の高い研究会・探訪会を堅持するため、年間開催回数を絞り込む。 詳細は、関連頁又は同研究会制作の「美産会08総合パンフ」で。 |
 新聞記事
|
3月19日(水):再び社会的関心を集め始めた日本のパブリックアート?昨年からその兆候が顕著になってきた、日本におけるパブリックアート(公共の場に進出して、様々な役割を果たすアート‥杉村解)への社会的関心が、再び戻ってきた事例を数件紹介。 1 新聞媒体(東京版各紙朝刊)と電波媒体(TV他)各社が、本日付けで岡本太郎の原爆炸裂を描いた巨大壁画作品「明日の神話」(1960年代にメキシコで制作・行方不明に。2003年同地で再発見・日本に里帰り修復、東京都現代美術館で現在公開中)の恒久設置場所が、現在地下鉄新線乗り入れ工事中の渋谷駅、「渋谷マークシティ」内の連絡通路壁面に決まった旨記事、写真入りで掲載・報道。 2 パブリックアート番組の制作を企図する某局ラジオ番組制作者のPA研究所へのヒアリング。日本と海外、特にアジア諸国における「社会づくりとアートの働き」に焦点を絞った映像番組制作構想のためPA研究所へ情報・アドバイスを求めてきた某社映像プロデューサー等々、パブリックアートへの関心者が、学生・研究者を含めて増加中。 3 PA研究所は、これらの兆候に合わせて「パブリックアート研究会」を、この4月から始まる地域美産研究会、第6年度活動の一つとして復活、第1回研究会について近々中に公表予定。 問合せ:パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132 |
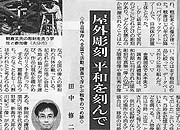 日経新聞記事
|
2月18日(月):日経新聞朝刊文化欄(東京本社版)が、 大分市で屋外彫刻像の保守管理を始めたNPO代表、田中修二氏が記述した 「屋外彫刻 平和を刻んで」掲載。田中修二氏(大分大学淳教授)が所属する大分大学は、“今年から2年間、大分市内50ヶ所の屋外彫刻を保守管理し、その後の継続的な管理のあり方を検討する”との事で、先ごろ学生、一般市民と一緒に市の中心部にある遊歩公園の、佐藤忠良作「聖フランシスコ・ザビエル像」など彫刻7体の手入れ作業を行ったとの内容。 日本が、バブル経済崩壊後10余年の停滞を経て、ようやく成熟期入った観を見せ始めたこの頃、明治以降、特に今次の大戦後、日本各地の都市づくりに合わせて美術館から屋外に出たアート作品たちの保存・管理を志向する人々が実践活動を始めたことは、大変喜ばしいこと。同記事中に紹介された「屋外彫刻調査保存研究会」は、黒川弘毅氏(武蔵野美大教綬)がこの分野の専門家たちに呼掛けて設立された団体で、今年度から藤嶋俊会氏(美術評論家)が会長就任とのこと。 問合せ:日経新聞東京本社Tel 03-3270-0251 パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132 |
 桑野医療施設研究会
|
1月19日(土):地域美産会第52回催事: 美産会世話人 桑野隆司研究会 『いま病院設計が抱える課題とアートの導入』 16~18時PA研究所図書室日本の病院設計の世界は、少子高齢化、経済の停滞・価格低廉化・省エネ化と、環境の変化に見合うハード・ソフト両面にわたる設計技術が求められているが、この分野の日本のリーダーの一人として、長年それらの設計・監理・コンサルティング業務に携わってきた当美産会の世話人、桑野隆司氏からその情況を同氏の代表作「川崎市立川崎病院」や、海外での取り組み事業を事例に、病院アートの導入例を含めて熱く語ってもらった。交歓会は青山ダイヤモンドホール「セブンシーズ」で。 問合せ:パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132 |
 1月10日の二見浦
|
1月10日(木):年始を寿ぐ日本の神々、伊勢二見裏の「夫婦岩」の美今年の元旦は、関東周辺だけが晴天の初日の出に恵まれたようだが、各地の神社はそれなりの天候の下で初詣の人々で賑ったとの報道だった。私(杉村)は、社の鳥居を日本の優れたパブリックアートと評価した米国の環境美学研究家、バーバラ・サンドリッセ女史の視点に共感して以来、地域美産会の会員たちと各地の神社を訪ねてそれならではの土地柄に見合う鳥居美を味わっているが、並行して正月の神社を各地に訪ねて新しい注連縄に飾られた鳥居をくぐり、拝殿前で年賀を祈ることも習慣となり、今年も元旦には地元の川崎市の驚神社、明治神宮、靖国社、そして10日(木)には伊勢を訪ねて内宮・外宮にも足をのばし、日本ならではの清廉美を体感してきた。伊勢神宮の静謐な自然のたたずまいに座す神の座の美は、いつお訪ねしても深く心に訴える何か感じるが、今回の初詣の旅では、正月の新注連縄を張った二見浦の「夫婦岩」が、薄明の波間に揺れながら静かな美をつくっていたことが、特に印象的だった。 問合せ:パブリックアート研究所、Tel 03-3407-9132 |
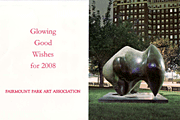 フェアマウント PA協会からの賀状
|
12月26日(水):今年も米国 Fairmont Park Art Association より年始賀状頂戴今年もパブリックアート研究所へ、米国フィラデルフィアのフェアマウント パーク アート協会(Fairmont Park Art Association)から、同市の「JFKプラザ」を飾るヘンリー・ムーアノブロンズ像“Three-Way Piesce Number 1”掲載の、2008年を祝す賀状が届いた。同協会は、パブリックアートと都市計画との統合を目指し、1872年に創立された米国最初の民間非営利団体で、フィラデルフィア市とその周辺におけるパブリックアートの制作・設置、広報・解説、保存等に取り組んでいることで有名。同協会のホーム頁、 www.fpaa.org を開くと、その歴史、現在実施中のプログラム、フィラデルフィアに設置された100以上のパブリックアート作品解説などを通じて、米国におけるパブリックアートの現状を知ることができる。 |
 東京丸の内仲通り
|
12月23日(日):今年の年末も各地でアートフルなイルミネーション盛ん。今年の年末年始(年末のみ含)も、札幌大通公園(第27回さっぽろホワイトイルミネーション)仙台市定禅寺通り(2007 SENDAI光のページェント)、東京丸の内(丸の内イルミネーション2007)、神戸(神戸ルミナリエ)、福岡(天神光のファンタジー2007)など、全国各地で大型イルミネーションイベントが開かれている。これらのイルミネーションデザインは、地球環境に配慮し省エネ技術に裏づけられながらも、日本の文化成熟度深化に合せて大人の観賞に耐えるアートフルな作品たちに進化中。 |
- 過去の最新ニュース欄掲載分は、年度ごとに「パブリックアートの動き」として纏めたものを、 パブリックアート研究所図書室にて閲覧又は有料送付で入手可能。 尚、著作権はパブリックアート研究所に属し、無断転用は法律違反となります。