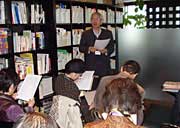過去の催事
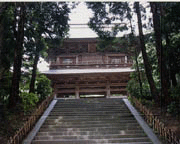 北鎌倉 円覚寺
 円覚寺山内 松嶺院での講義
|
第54回催事 6月21日(土):地域美産研究会特別企画催事 『北鎌倉心(こころ)塾』を北鎌倉円覚寺/東慶寺山内で開催。参加者は28名(内外人6名)。心の美産研究会シリーズそのⅣ『北鎌倉心塾』と題し、日本の公徳心(Public Manner)発祥の源を北鎌倉に尋ねる企画。12世紀の中頃、北条時宗の請により南宋から渡来した臨済宗高僧、無学祖元が、僅か18才で日本の最高指導者となり蒙古襲来に対峙した時宗の心をどう導いたか。それが、日本の武士道/公徳心の形成、侘びさび文化の結実にどう繋がったかを、鈴木大拙「禅と日本化」、網野善彦北鎌倉円覚寺「蒙古襲来」他を引用しながら、杉村荘吉(パブリックアート研究所代表)が解説し、円覚寺・東慶寺等にゆかりの美産たちを普段は非公開の美産(松ヶ岡文庫など)を含めて訪ね、座禅・茶礼・往時を偲ぶ精進料理も体感する特別企画催事。 |
 発表会
|
第53回催事 4月14日(月):地域美産研究会の第6年度の活動事業開始で「発表会/パーティ」。平成14年(2002年)12月始まった地域美産研究会の活動は、この4月から第6年度に入り、下記の特徴を基に実施。
|
 PA図書室でのプレゼン
|
第52回催事、美産会世話人 桑野隆司氏研究会『いま病院設計が抱える課題とアートの導入』1月19日(土)16時~18時 PA研究所図書室。参加者14名。日本の病院設計の世界は、少子高齢化、経済の停滞・価格低廉化・省エネ化と、環境の変化に見合うハード・ソフト両面にわたる設計技術が求められているが、この分野の日本のリーダーの一人として、長年それらの設計・監理・コンサルティング業務に携わってきた当美産会の世話人、桑野隆司氏からその情況を同氏の代表作「川崎市立川崎病院」や、海外での取り組み事業を事例に、病院アートの導入例を含めて熱く語ってもらった。交歓会は青山ダイヤモンドホール「セブンシーズ」で。 |
 大阪美産会Ⅱ研究会
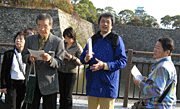 大阪美産会Ⅱ探訪会
|
第51回催事、大阪の美産会員 橋本 完さん企画・案内の大阪美産会Ⅱ『大阪城の内外になにわの聖地を尋ね、地歌舞の奉納を観賞する』11月17日(土)~18日(日)参加者;地歌舞20余名、交歓会11名、探訪会7名。大阪城の前身石山(大坂本願寺在所)は、聖地として民衆から崇められた処。大阪城とその周辺に散在する史跡名所は、古典的風水による設計思想を導入して造られている。17日(土)はそれらの事を橋本さんから学び、古澤侑峯師匠による地歌舞の奉納観賞、界隈の料亭「うを清」で歓談。18日(日)は、先ず天守閣・石山本願寺跡を含む大阪城内城の史跡訪ねた後、大阪城から始まる上町台地を南に歩いて、飛鳥奈良時代、中世、江戸、明治に連なる諸史跡に立ち寄り、再び北に戻りながら天武天皇時代の「なにわの宮」跡地を訪ね、それらを最後に大阪歴史博物館で再学習した。天気晴朗だが寒気が厳しい2日だった。 |
 旧岩槻城黒門
|
第50回催事:埼玉県立近代美術館学芸主幹/世話人 伊豆井秀一さんが企画・案内するさいたま美産会‐Ⅵ『人形の町、岩槻の地域美産たち』10月13日(土)参加者16名。岩槻は明治4年(1871)の廃藩置県に際して、県庁所在地に選ばれる程埼玉県の中心地の一つで、その歴史は、室町時代(1457年)に大田道灌が岩付城を構えた頃にまで遡る。平成17年4月にさいたま市岩槻区に変わった岩槻市は、「人形の町」としても有名だが、同時にこの地ならではの歴史文化を伝える数々の建物美産を今に伝える。当日は程好い晴れの天候で、人形づくりの老舗「東玉」人形博物館で江戸時代の「享保雛」から現代に至る人形の歴史を、館長の解説で聴講してから街に出た。江戸時代から遺る染物業大店舗、元警察署として建てられた岩槻郷土資料館、岩槻藩校「遷高館」の復元建物、岩槻城長屋門「黒門」や岩槻城址などを、さいたま美産研究の第一人者、伊豆井秀一さんの案内・解説で遍歴。交歓会は、岩槻の迎賓館と言われる老舗料亭「ほていや」で。 |
 心の美産会の一こま
|
第49回催事:パブリックアート研究所代表杉村荘吉による『新渡戸「武士道」8つの要点を参考に、日本と諸外国の「人としての礼議」を探り話し合う』9月20日(木)夕 PA研究所、参加者7名。新渡戸「武士道」の8つの要点、義、勇、仁、礼、誠、名、忠、克の紹介後、武士道精神西欧騎士道における「忠」との相違、ユダヤ教などの選民意識と他者蔑視、武士の時代の女性の役割が飛んだ。次に、21世紀をアート・文化力競争の時代、騎士(武士)道精神に基づく社会運営時代と位置づけて、今世紀に求められる日本の国の品格、女性の品格を論じ合った。そこから話は、今月引退した安倍首相の品格と業績評価に飛んで、朝日新聞のジャーナリズム史上に汚点を残す“安倍いじめ”の醜さ及んで、マスコミ各紙・評論家などの品格の無さが指摘された。身近な話題ゆえに参加者間に熱い議論が飛び交い、終了後の「ほの字」における交歓会でも、ホットな議論が飛び交った。 |
 高岡市、国宝瑞龍寺
 PAF IN いなみ、井波瑞泉寺太子堂
|
第48回催事:富山県のパブリックアート研究/実践リーダー、富山大教授 長谷川総一郎さん企画案内による特別催事、富山美産会; (1)「パブリックアートによる地域再生事業と歴史美産を富山県に訪ねる『いなみ・高岡地域の活性化とパブリックアート/歴史美産 』」平成19年8月25日(土)~27日(月)参加者16名。 (2)「パブリックアートフォーラム IN いなみ」8月26日午後 井波、瑞泉寺太子堂 参加者50名。富山県高岡市は、大友家持が国主として赴任して以来、地域が造り遺した歴史と産業美産活用の街中再生事業を遂行中。その南に在る井波の町(南砺市井波地区)は一向宗徒が暮す町で、名刹「瑞泉寺」はその象徴。町内には欄間や獅子頭等を刻む木彫工房が今日迄継承、 300人の木彫家達が伝統工芸と芸術作品の制作に匠技を競う町。 催事企画者の長谷川総一郎氏は、富山県を代表する彫刻家、芸術文化教育研究・指導者、地域再生アドバイザー、パブリックアート研究/実践家。今夏は、長谷川氏の発案で平成3年以来、4年に1度開く「いなみ国際木彫刻キャンプ」の開催夏であることから、高岡・井波のパブリックアートと歴史美産を活かす地域再生事業の現場を訪ね、井波では「パブリックアートフォーラム IN いなみ」に参加した。 また25日は、隣接の八尾市「風の盆」のリハーサル風景を、吉川和哉氏(美産会員)の引率で見学。27日には地元の北日本新聞がフォーラム開催の模様を朝刊で報道。 |
 臨春閣を臨んで藤島さん解説
|
第47回催事:神奈川の美産研究第一人者、藤島俊会さんが解説する横浜市の名園「三渓園」研究・探訪会、平成19年6月23日(土)。参加者、美術系学生を含む13名。横浜市の三溪園は、生糸貿易で財を成した実業家三溪が造った個人庭園だが、1906年(明治39)に一般庶民に公開された歴史を持つ名園。175,000m2に及ぶ園内には京都や鎌倉などからの歴史的価値の高い建造物(重要文化財10棟・横浜市指定有形文化財3棟)が移築配置。1908年(明治41)に外苑、1923年(大正12)に内苑が完成。三溪存命中は当時の新進芸術家の育成支援の場となり、前田青邨の「御輿振り」、横山大観の「柳蔭」、下村観山の「弱法師」など、多くの近代日本画の代表作品が園内で誕生。先の戦災で大被害を受けたが、1953年(昭和28年)横浜市に譲渡・寄贈以降、財団法人三溪園保勝会が復旧保全管理に努める名園。 梅雨期にも係らず当日は晴天に恵まれ、長年三渓園研究に研鑽を続ける神奈川の美産研究第一人者、藤島俊会さんの解説が随所に光った美産会だった。交歓会は横浜中華街「吉兆」。 |
 下谷、鬼子母神で
|
第46回催事:美産会アドバイザー 外山晴彦さん企画案内「庶民信仰の石仏美産探訪会Ⅱ“江戸の隠れ家町、下谷・根岸の石仏と富士塚”」平成19年5月26日(土)、参加者15名(内2名は外国人)。台東区の下谷・根岸地区は上野公園の北東に位置して、江戸時代は「根岸の里のわび住まい」と言われるくらい閑静な地で、江戸から大正にかけて多くの文人墨客が住むとともに、「恐れ入谷の鬼子母神」「朝顔市」など庶民の信仰・文化美産の多くが随所に遺る土地柄。 今回の石仏探訪会では1600年代に建立された初期型庚申塔や三猿塔庚申塔、性器付狐が守る稲荷神社、国の重要民俗文化財に指定された富士塚などを、地域美産会アドバイザーの外山晴彦さんの案内と解説でじっくり探訪。参加者は15名で、内2名は外国人(オーストラリア、ベルギー)。交歓会は、界隈評判の蒲焼割烹、「根ぎし宮川」で。 |
 概括報告説明会
 午餐会
|
第45回催事:「年度末パーティ:今期報告/来期概括会と感謝午餐会」、平成19年3月10日(土)10:00~14:30、PA研究所・ウラク青山。参加者17名。3月は第4年度活動の最終月に当ることから、卒業期と学校休み期に入る後半を避けて早目の10日(土)に、(1) 午前中、今期の活動内容を収支推移も含めての報告会、4月から始まる第5年度活動の概括説明会、(2) 場所を変えて、45回に達した美産会活動へのご支援感謝と参加者同士の交歓を目的に、「感謝午餐会」を外苑前「ウラク青山」で開催。 午前の会では藤島さんによる、同氏企画案内美産会の過去とこれからを概括する話も興味深い内容だった。 |
 伊豆井さん探訪先概括説明
 彩々亭での建物解説
|
第44回催事:美産会世話人 伊豆井秀一 企画・案内「さいたま美産会‐Ⅴ」『行田~古代ロマンへの誘い、そして足袋蔵』研究・探訪会:平成19年2月17日(土)、参加者15名。埼玉県北部に在る行田市は、県名が同市大字埼玉(さきたま)に由来するように、古墳時代から拓かれた地域で、他所には無い歴史と産業美産たちが残る文化都市。 「稲荷山鉄剣」の発見でその名が全国に知られた稲荷山古墳を擁する埼玉古墳群、浮き城と呼ばれる豊かな水と緑に囲まれた美しい忍城跡、江戸中期に下級武士が始め明治後の機械化で一大産業に成長した「足袋」生産地としての建築を含む文化遺産など、埼玉(さきたま)文化が創った歴史・文化・産業・自然美産達を、地域美産会世話人で埼玉県立近代美術館学芸主幹の伊豆井秀一さんの案内で探訪。 当日は上記美産に加えて、国宝「稲荷山鉄剣」、埼玉(さきたま)古墳丘、昭和初期建築の銀行、豊な伏流水から美酒を造る横田酒造、行田一の足袋大尽旧邸宅(現在料亭、彩々亭)等の見学、同亭での交歓会、と上質で中味の濃い会だった。 |
 外山さんの解説
|
第43回催事:美産会アドバイザー 外山晴彦さん企画案内「庶民信仰の石仏美産探訪会“日暮里から駒込へ、上野台地に江戸の石仏美産を訪ねて、庶民信仰の形と楽しみを学ぶ ”」平成19年1月20日(土)、参加者13名西郷隆盛の銅像が立つ上野から王子へ続く上野台地は、谷中の寺町から桜の名所飛鳥山まで、幕府が政権を裏から支える庶民の為に、息抜き娯楽の場として整備した地。谷中から日暮里・田端に連なる寺町台地と北へ下り駒込に到る小道筋には、江戸庶民の信仰を司る小さな寺院たちが散在し、様々な石仏たちや神仏混交の足跡も遺る大変面白い小道通り。境内では庚申信仰のシンボル、庚申塔や供養塔、江戸に居ながら富士登山ができる富士塚など、江戸の庶民美産たちが散見できる。 企画案内人は、神社寺院や野仏探訪の第一人者で地域美産会アドバイザーの外山晴彦さんで、難しい事柄を易しく解説する同氏の解説は、参加者を大変魅了した。お昼に推薦した日暮里の蕎麦店「川むら」と、交歓会を開いた駒込の「やきとり松本」の味もまた、大好評だった。 |
 心の美産研究会Ⅱ
|
第42回催事:杉村荘吉と田中啓介会員による、心の美産研究会Ⅱ『新渡戸「武士道」のエッセンス/今なぜ武士道か』12月16日(土)午後 PA研究所、参加者12名心の美産研究会Ⅱは、8月開催の心の美産研究会Ⅰの結論、今後の当該研究会は“新しい時代に見合う日本のPublic Manner探し”をテーマに開く研究会に改変へ向う序編として開催。前回出来なかった“新渡戸『武士道』の真髄・エッセンス”の解説を美産会代表の杉村荘吉が、“新渡戸『武士道』、その周辺”を田中啓介会員が「女性と武士道」を含めて語った。参加者は12名で、男女6名ずつの構成だった。 同研究会の終了後、忘年会を兼ねた交歓会が近所の「ほの字」で開かれ、11名が参加し歓談し今年の美産会活動を終えた。 |
 清水道子さん研究会講演
 大阪最古の幼稚園、愛珠幼稚園
|
第41回催事:大阪美産会員 橋本 完さんの大阪美産研究・探訪会Ⅰ『日本の近代医薬発祥の地・大阪に薬種問屋の歴史・文化美産を訪ねて、大阪再生の魅力づくりを考える』研究会:11月22日(水)夕、探訪会:11月23日(祝日)‥参加者20名(10名が大阪から)大阪の発展は、7・8世紀上町台地の“難波の宮”造営に端を発し、太閤秀吉の町割り整備、江戸幕府の「天下の台所」づくりが現在の「水都大阪」に繋がる。「道修町」は太閤秀吉の街割りで誕生した町筋。江戸時代には中国・オランダ等からの輸入薬は一旦道修町に集まり、全国に流れ、現在も大手製薬会社の本社が多く存在し、全国で流通する薬剤の半分を取引する町に発展。また道修町は、日本近代医学の祖、緒方洪庵(1810-1863)開校、福沢諭吉、橋本左内等が学び、後に「大阪大学」へ発展した「適塾」が残る町、大阪の上質文化と伝統を継承する地域として著名。 研究会では、「伝統を守るなにわの会」代表・清水路子さんが「なにわコトバ」、道修町・船場の慣わしと文化を、橋本完さんが、道修町の神農祭と漢方薬との繋がりなど話した。探訪会当日は道修町の護り神、少名彦神社の年に一度の「神農祭」の当日で、祭で賑わう中で、同神社参拝と別所宮司による「くすりの道修町資料館」解説、適塾や大阪最古の幼稚園「愛珠幼稚園」と銅座跡に立ち寄り、道修町の名家、ボンドの小西家では五代目当主から、大阪の服部時計店と言われた旧生駒時計店の生駒ビルでは同じく五代目社長から、事業と建物の歴史の話を聞く探訪会となった。 |
 国分寺、都立殿ヶ谷戸庭園
 国分寺跡公園中学生演奏
|
第40回催事:高橋良孝会員の企画探訪会『高橋良孝さんと、秋の草花樹木を武蔵国分寺界隈に訪ねる』平成18年10月21日(土)参加者9名野草花の会副会長で自然植生解説の第一人者、高橋良孝さんが企画する、秋の武蔵国分寺界隈の草花と樹木探訪会。薄日の秋盛りの午後、都立殿ヶ谷戸庭園(旧三菱財閥岩崎別邸)の逍遥から始まった国分寺界隈の秋を訪ねる探訪会は、参加者が比較的少人数だったこともあって、訪問先夫々の花草樹に加えて道筋の植物解説にもたっぷり時間をかけることが出来た。 一行は、殿ヶ谷戸庭園のあと、お鷹の道、真姿の池湧水群、万葉植物園、武蔵国分寺跡公園を訪ね、また国分寺跡公園では、隣接公立中学の女生徒トリオの管楽器演奏を楽しむハプニングもあって、大変心充たされた午後となった。そのムードは夕方の交歓会(国分寺駅前和楽亭)にも持ち越され、来期の高橋自然探訪会は、高橋ファンを代表して女性会員平岡さんと渡部さんが高橋さんと相談して企画づくりを推進することに決まった。 |
 白拍子の舞謡
|
第39回特別催事:岡林 馨会員の鎌倉美産研究・探訪会Ⅳ『武家社会に生きた女性たちを史跡に尋ね、鎌倉一の名舗「鉢の木」で白拍子の舞謡と鼓を鑑賞、武家のご膳を賞味する』:平成18年(2006)年9月30日(土)参加者;研究探訪会21、鉢の木会30名鎌倉生まれの岡林 馨(美産会員)さんは、実業界退職後鎌倉市の有力者のたちと鎌倉市まちづくりに尽力中。今回の美産会は、「武家の古都・鎌倉」世界遺産申請に合せて、鎌倉の新しい魅力開発を企図し、その文化と産業活性策を織り込んだ催事。 第1 部研究会では、「武家社会に生きた女性たちを史跡に尋ねる」を、鎌倉生涯学習センターで学び、第2部探訪会では、北條政子の寿福寺や東慶寺などを尋ねて武家社会の女性たちの歴史を探訪。第3部は「その芸と食を体験する」で、北鎌倉の精進料理の名店「鉢の木」で、「白拍子」の舞謡の復活を志して公演活動中の桜井真樹子さんによる、義経の愛妾で白拍子の名手、静御前が義経を慕って鶴岡八幡宮で舞った「静」の舞謡鑑賞、その後「鉢の木」亭主の解説・濁り酒と共に、目下開発中の「武家のご膳」を賞味。 大変中味が濃い企画で、参加して本当に良かったという感想が、数多く寄せられた。 |
 撮影、PA研究所
|
第38回催事: PA研究所代表 杉村荘吉の企画構成、新渡戸稲造の「武士道」 英語版読書会、パブリックアート研究所: 8月23日(水)18時~20時、参加者13名。日本の人々が暮らしの歴史を通して練り上げた自律自尊の精神を、心の美産として捉え、その普遍性と国際性を新渡戸稲造の「武士道」英語版に尋ねる。当日はシンガポール大使館一等書記官を含む、一般市民から専門家まで13名が参加。本の概要、新渡戸の経歴と当時の日本を巡る国際環境等を、杉村と戦後日本の海外事業開拓者で財界の国際リスクマネジメントアドバイザー、江川淑夫の解説をまじえて学習し、自由な意見を交換。次回からは、新渡戸「武士道」以外からも「日本道徳」の源を探り、次の時代に必要な日本の道徳づくり研究会への転進が要望された。 |
 ノーマン博士の講演と研究会
 川崎市平和公園の探訪会
|
第37回特別催事:日本のパブリックアート、その変遷と意義・役割『日英2名の研究者が、日本のパブリックアートの変遷、その意義・役割を語り、事例を川崎に尋ねる』研究会(東京):7月19日(水)参加13名、探訪会(川崎):7月22日(土)10名 研究会では、神奈川芸術文化財団で長年パブリックアートの調査研究・評論活動を続けてきた当会の世話人、藤島俊会さんと、昨年英国Leeds大学から “The culture and Practice of Public Art in Japan”研究で博士学位を取得した英国人Elizabeth H. Norman(エリザベス・ノーマン)さんの二人が、夫々なりの視点による日本のパブリックアートの変遷とその意義役割などについてアカデミックな講演をした。 英語で日本のパブリックアートを語ったノーマンさんの講演は、外国人らしい視点からとてもユニークな講演であった。参加者にとっても久々の外国人のしかも博士による説明に新鮮な印象を感じた。通訳も兼務された杉村代表、大変お疲れ様でした。 探訪会では川崎市を訪ねて、つい最近JR川崎駅西口に完成した「ミューザ川崎」のアートワークたちと、20年前に同駅東口につくられたパブリックアートたちなどを、藤島俊会さんの案内と解説で比較検証した。参加者は、ダイナミックな変身を続ける川崎市に圧倒された。交歓会は川崎市民が古くから通うJR川崎駅東口「とくり」で地元の味を楽しんだ。 |
 研究会、PA研究所
 探訪会、札幌モエレ沼公園
|
第36回催事 札幌の最新美産研究・探訪会『最近完成したアートたちを訪ねて、サッポロの都市と観光の新しい魅力を探る』研究会(東京):6月22日(木)参加13名、 探訪会(札幌):7月1日(土)10名 評論家の浅田彰は『この夏行くとしたら、やっぱり札幌郊外のモエレ沼公園でしょう。モエレ沼のゴミ捨て場を公園に変えよと、イサム・ノグチが88年に亡くなるまで頑張ってマスタープランをつくった‥‥‥公園そのものが彫刻だっていうコンセプトでさすがに壮大だよ』と語っているが、今回の会は、環境デザインの専門家で当会アドバイザー/会員の後藤元一さんの企画力と人脈力で、イサム・ノグチ最後の企画・デザインプランを具現化した札幌市モエレ沼公園と、札幌の文化都市づくりの拠点・札幌芸術の森などに、都市と観光の新しい魅力を検証した。 研究会では、中国黄土地帯の洞穴住居研究家で目下モエレ沼公園研究者として売り出し中の八代克彦、ものつくり大学助教授が、「モエレ沼公園に託したイサム・ノグチのメッセージ」と題して、その作成意義・特徴・フォルムの解析等を画像を多用して解説し、質疑に応答した。 札幌探訪会では、後藤元一、山本仁(札幌市吏員で建設計画づくりから参画、この3月までモエレ沼公園長就任)両氏が案内解説の予定だったが、山本さん急逝という思わぬ事態から後藤さん単独で行われた。地元からの参加者(画廊オーナー野口さん、産經新聞對馬さん)を加えた一行は、大通公園のノグチ・ブラックスライドマントラ、石山緑地アートパーク、芸術の森や野外彫刻群、モエレ沼公園の大規模ノグチ作品各種に触れたり登ったりしながら、それらの魅力と審美価値を検証。モエレ沼での壮大な噴水劇観賞、サッポロビール園での元祖ジンギスカン料理交歓会も参加者たちを魅了し、05年度の同市観光施設の最多訪問先と訪問者数はモエレ沼公園、708,410名という調査結果を体感。 |
 錦市場 京野菜「川政」前で
 秦家での午餐会
|
第35回催事 京都の美産研究・探訪会‐2『京都の食文化の源を錦市場に尋ね、錦が育んだ京料理の粋を秦家で味わう』研究会(東京): 5月17日(水)18:00~20:00 参加者10名 探訪会(京都): 5月20日(土)10:30~15:30 参加者11名 昨年大好評の「京都美産会‐1」に引き続き、「京都美産会-2」を開催した。今回は会員で寺社修復を手がける建築設計家・田中 哲さんの企画による京都の錦市場に焦点を当て、京都食文化の源を探訪する会となった。 最初に錦市場振興組合の会議室で三田冨佐雄理事(川魚「のとよ」代表)から、京都の錦市場が室町中期頃に寺院等への食材供給を担って発生したこと、現在は道幅3.2m・長さ390m・店舗数147店に成長、姉妹都市であるイタリアのフィレンツェとの深い関係など、興味の尽きない解説を受けた。その後の市場案内では、特に、田中哲さんが今回のメインテーマとした京野菜の「川政」で、京野菜についての活発な質問が相次いだ。 探訪後は、錦市場の食材がどのような京料理に変身するのかを実際に体験するため、昨年も大好評だった秦めぐみさん(秦家)に再び協力をお願いし、午餐会を開催した。ひいき筋の「のとよ」さん等、錦市場からの入手食材が極上の京料理に仕上がる実際を、秦家奥座敷で銘酒と共に味わった。その後めぐみさんから各部屋の説明を詳しく受け、京の町家生活の審美性に触れた。今回も内容の濃い研究・探訪会となり、参加者から称賛の声が多数聞かれた。 |
 探訪前のガイダンス
 高橋さんの説明に聞き入る会員
|
第34回催事 国営昭和記念公園 春の特別見学会『春爛漫の植生たちを訪ねる』探訪会:平成18年4月1日(土)11時~16時30分(参加者 16名) 参加者16名は、満開の桜を目的に来園した大勢の花見客や家族連れに混じって、午前11時に快晴の国営昭和記念公園西立川門に集合した。案内と解説は、昨年秋の探訪会に引き続き、地域美産会員で昭和記念公園工務課長の山野辺信治さんと、同じく会員で野草友の会副会長、NHK学園講師の高橋良孝さん。 1983 年10月に開園した国営昭和記念公園は、昭和天皇在位50年を記念して造園された国立公園。 四季の変化に対応して豊かな季節感をつくりだす花々と樹林たちを配した緑の大空間や、本物の日本庭園づくりに徹した庭と和風建築は、この春最高の陽光の中で極上の美しさを顕現した。今回は、昨秋完成した「花みどり文化センター・昭和天皇記念館」もゆっくり案内してもらった。 高橋さんの春に萌えたつ草花と樹木たちの案内・解説は、常に多数の女性参加者たちを魅了して、まれに見る晴天の中「春爛漫の植生たちを訪ねる“特別見学会”」は、前回以上に充実し、春到来を充分に堪能する会となった。 交歓会は立川駅前の「あらい寿司」で開催。晴天に感謝しつつ、改めて山野辺信治さんと高橋良孝さんへの賛辞が参加者全員から述べられ散会した。 |
 研究会
 氷川神社を探訪中
|
第33回催事 さいたま美産研究・探訪会-4【さいたま新都心、そして氷川神社周辺の美産】研究会:3月15日(水)18:00~20:00(PA研究所図書室、参加者13名) 第3 年度最後の催事として伊豆井世話人の企画による、さいたま美産研究・探訪シリーズ-4。永い歴史をかけて「今日までのさいたまづくり」を担った旧大宮市の発展の礎(いしずえ)、武蔵(むさしの)国造(くにのみやつこ)の鎮守として大和朝廷成立以前から在ると言われる武蔵一宮、氷川神社とその周辺の文化的美産たちをスライドを使って説明。 探訪会:3月18日(土)さいたま新都心~氷川神社~盆栽村(参加者17名) 午前11時さいたま新都心に集合し、埼玉県の明日の発展を担う「さいたま新都心」駅前高層ビルの最上階に上り、眼下に広がる新しいさいたまを俯瞰。街区を彩る代表的なパブリックアートを観賞し「明日のさいたまづくり」を実感し、氷川参道 → さいたま市立博物館 → 氷川神社へ。氷川神社では馬場権禰宜から神社の縁起を拝聴した。その後、埼玉県立博物館 → 関東大震災の後、東京の植木職人の移住により成立した盆栽村の清香園 → 北沢楽天の漫画会館などバラエティに富んだ見学を楽しみ、四季の家で現地解散。希望者のみ「庄家」の交歓会へ。今回の探訪会は、長年地域の美産に係わってきた伊豆井世話人の存在感を改めて感じる会となった。 |
 講演風景
 交歓パーティ参加者
|
第32回:特別催事:(1)加藤源会員(日本都市総合研究所長)特別講演会「人を魅きつける都市空間と地域美産」、(2)杉村世話人会代表「来期活動案発表会」、(3)年度末交歓パーティ平成18年(2006)2月18日(土)10:00~16:00 地域美産会第3年度の活動終了を来月に控えた特別催事として、(1)当会のアドバイザー/会員で日本の都市設計デザイン分野の第一人者加藤源さんによる講演会を10:00~11:30に、続いて杉村世話人会代表による来期活動案発表会を12:00~13:00 PA研究所図書室で開催。加藤さんの講演は、「人を魅きつける都市空間とは」というテーマで、都市空間の魅力づくりを「個性」、「包容力」、「発見と感動」、「参加感」など12の魅力項目から同氏が体験した国内と外国の都市空間を写真を交えて紹介。 (2) 杉村代表による「来期活動案発表会」は講演会に引き続いて行なわれ、来期活動案づくりは昨年秋匿名で実施の会員アンケート調査回答を参考に行なったこと、会員企画による札幌、大阪など遠隔地催事を増やすこと、学生無料招待事業開始と活動力強化の為に寄付金制度導入を説明。 (3)午後からの交歓パーティは表参道最寄のカフェ「Jazz bird」で行われ、参加者が同一話題を語り合えるに最適な場と雰囲気の下に中味の濃い交歓を持った。参加者は富山からの長谷川会員を含めて(1)(2)が18名(3)が11名。 |
 研究会 PA研究所にて
 神田明神の探訪
|
第30回催事: 神田美産研究・探訪会『神田界隈‥湯島聖堂から古書の街・学生の街を歩く』研究会(PA研究所図書室); 12月14日(水) 18:00~20:00 (参加者8名) 「江戸っ子だってねえ」、「神田の生まれよ」と、いなせなお兄さんが啖呵を切るほど、神田は江戸の代名詞。といっても神田は広うござんす。今回は地域美産会の世話人藤嶋俊會さんが企画・案内する「神田界隈を歩く」の研究会が開かれ、古本街の地図や資料を使って詳細な説明があった。 探訪会(東京神田界隈); 12月17日(土) 10:30~19:00 (参加者14名) 「神田界隈―湯島聖堂から古書の街・学生の街を歩く」と題して開催された探訪会は、まずは神田川を挟んで湯島聖堂へ。湯島聖堂では境内で偶然お会いした石川忠久、斬文会理事長(著名な漢詩文学博士)に聖堂の解説を拝聴、僥倖に感動。その後、神田明神、万世橋を渡って神田駿河台へ。異国情緒豊かなニコライ堂を見て、アールデコ様式の「山の上ホテル」では、コーヒーを飲んで休憩。文化学院を経て神田神保町へ、有名な出版社や個性豊かな古書店など神保町の雰囲気を満喫。探訪会終了後の交歓会は、老舗のビヤホール「ランチョン」(明治42年創業)で忘年会を兼ねて開催、一年間の探訪会の話題などを語り合い散会。 |
 「やんも」でのランチ
|
第31回催事:特別企画『米国人環境美学研究家、バーバラ・サンドリッセ女史とのフリートーク+ランチ会』PA研究所図書室+魚料理「やんも」;12月8日(木)10:30~19時 (参加者6名) 社や鳥居、桜や稲田等、日本の自然が織りなす日本ならでは環境美産たちの研究家バーバラ・サンドリッセさんが、一年ぶりに東京に立寄る機会を活かした特別催事。 緊急連絡のため小人数の会となったが、その分各参加者はサンドリリッセさんと充分懇談ができ、特に当日そのために富山から参加した長谷川会員をはじめ、愛甲会員のご子息(高校生)の飛び入り参加も含めて、午前中のトーク会、「やんも」でのランチ会、午後のカフェーでの続き会など、19時過ぎまで交流が弾んだ。尚会話は英語主体で行なわれた。 |
 研究会 PA研究所にて
 朝夷奈切通し
|
第29回催事: 鎌倉美産研究・探訪会Ⅲ『晩秋の鎌倉に、中世鎌倉名残りの寺社と切通しを訊ねる』研究会(PA研究所図書室); 11月16日(水)18:00~20:00 (参加者9名) 鎌倉同人会理事で郷土研究家、岡林 馨会員の企画・案内で「鎌倉シリーズそのⅢ」の研究会が開催された。鎌倉に幕府が開かれた歴史的経緯を辿り、その象徴ともいえる「切通し」と、現在、鎌倉市で積極的に推進中の「世界遺産登録」についてなどの詳細な説明があった。 探訪会; 11月19日(土)10:30~19:00 (参加者16名) 探訪会は、秋晴れのもと紅葉狩り、ハイカーなどで混雑する鎌倉駅からバスに乗り、先ず十二所神社から鎌倉七箇所の「切通し」で代表的な「朝夷奈切通し」を訪ねた。切り開かれた細い山道では足元に水も流れ、鬱蒼とした森と両側に切り立つ崖の中を歩いて、文字どおりの「切通し」を体感。その後、光触寺、足利公方屋敷跡碑を巡って英国チューダ朝建築様式の旧華頂宮邸テラスで昼食。午後は、報国寺の孟宗竹林を見て、浄妙寺、鎌倉市内最古の杉本寺、日本三天神の一つ荏柄天神社、鎌倉宮まで訪ね、晩秋の鎌倉を堪能。交歓会はフランス風洋食の老舗「小町園」でレトロモダンな洋食を味わい、今回の鎌倉探訪会の印象を語り合った。参加者全員が岡林会員に、良く研究・準備された分かり易い解説に賞賛と感謝を表しつつ散会した。 |
 高橋さんの説明を聞く
|
第28回催事 国営昭和記念公園、特別見学会10月1日(土)11:00~20:30(参加者20名) 爽やかな秋晴れの中、山野辺信治会員と高橋良孝会員の企画案内で、昭和天皇在位50年を記念して造園された国営昭和記念公園と、今年11月開園予定の「花みどり文化センター・昭和天皇記念館」(伊東豊雄氏などの設計JV)の特別見学会を開催。 日本ハーブの権威の一人、高橋さんの花々と樹林の説明は楽しく説得力に富み、多くの女性会員が高橋さんから離れられなくなってしまうという一幕も。日本を代表する美産として建築された第一級の日本庭園や茶室などの和風建築も山野辺さんの案内で細部まで拝見できた。見学会後の交歓会は、立川駅近くのいわし料理居酒屋「たかね」でいわし三昧を堪能しつつ、秋晴れにめぐまれた良き1日を語り合った。 |
 ちちぶ銘仙館前庭
|
第27回催事 秩父探訪会「~絹、信仰、そして・・・~」秩父市、9月17日(土)11:00~19:00(参加者16名) 秩父探訪会は「~絹、信仰、そして・・・~」のテーマで、伊豆井秀一(世話人・埼玉県立近代美術館学芸主幹)さんの企画・案内で、爽やかな初秋の秩父路で開催。 先ず「ちちぶ銘仙館」へ。技術継承者育成指導講師、横山敬司さんの解説で秩父銘仙の染め織りの工程を聞く。その後「番場町通り」から「買い継ぎ商通り」へ明治から昭和初期の町家建築の探訪。お昼は「武蔵屋」で秩父きってのざるそばを堪能。午後は秩父神社、武甲山の伏流水で銘酒を造る「武甲酒造」、江戸・薩摩切子で日本一のコレクションを誇る「ちちぶびいどろ美術館」へ。交歓会は、秩父いのしし亭」の猪の味噌煮鍋と秩父銘酒を味わい、まるで修学旅行のような賑やかな楽しい気分で家路についた。 |
 撮影、片倉嘉明
|
第26回催事 会員有志の企画 『納涼交換パーティー』表参道NHK青山荘、8月27日(土)14:00~17:00(参加者22名) アドバイザー/会員が、地域美産会の今後の活動について素直な意見や要望を述べ合い、楽しく交歓する納涼パーティーが、江田一夫会員ほか有志の発案・主催で開催された。今回は久しぶりにアドバイザー・会員の山岡義典さん(日本NPOセンター副代表理事)、富山県の長谷川総一郎さん(大学教授)なども参加して、多彩な知識と経験に裏打ちされたスピーチをされた。また札幌や富山県の井波地方で地域美産会を開催する企画案も提案されて、賛同の拍手を浴びた。引き続き会員各位のスピーチがあり、地域美産会への思い、希望などを語り合い、最後まで和やかな雰囲気の中で、参加者全員が何かを得たという満足感一杯のパーティーとなった。 |
 研究会 PA研究所にて
 探訪会・明治神宮
|
第25回催事 鳥居の研究・探訪会 『鳥居のカタチや生い立ちを学び、その美や地域との融合性を体感する』 杉村荘吉(PA研究所代表、世話人会代表)研究会(PA研究所図書室); 7月23日(土)10:00~12:00 (参加者24名) 「鳥居のある風景」という写真集を出版したジョニー・ハイマス、「パブリックアートとしての鳥居、その不思議な魅力」を書いたバーバラ・サンドリッセなど、多くの外国人が「鳥居」や「鳥居のある風景」に魅了されています。21世紀を迎えた今日本人自身が、長い日本の暮らしの歴史から生まれたホンモノの美産たちに光を当て、この国ならではの美性や文化性を再評価し、これからの自分づくりや生活づくりに活かしていく必要があるのではないでしょうか。このような想いから杉村代表が発案した催事で、今回はその総括篇と位置付けて、鳥居の原点、歴史、種類、意味などを、海外の事例を含めて解説した。 探訪会(明治神宮、日枝神社など); 同日13:30~17:00 (参加者28名) 猛暑を心配したが、むしろ曇天で涼しい中、午後は明治神宮からスタート。権禰宜の高畠様より明治神宮境内を案内・説明をしていただいた。その後、秋葉神社→ 大松稲荷→虎ノ門金毘羅宮→山王日枝神社へと探訪した。交歓会は赤坂の割烹の名舗「ととや魚新」で開催し、参加者それぞれの感想を述べあい楽しい一日を振り返った。 |
 研究会 PA研究所にて
 探訪会 横浜中華街にて
|
第24回催事 横浜の美産研究・探訪会 横浜モダンを尋ねる PART IV 「中華街-ヨコハマの都市形成を歩く」横浜の美産研究会6月15日(水)PA研究所図書室(参加者12名)。 神奈川の美産たちに精通する元神奈川県民ホールギャラリー課長 藤嶋 俊会さんが企画・案内する「横浜モダンを尋ねる PART IV」の研究会が開催され、横浜中華街の誕生から現在まで、世界各地の中華街の話、そして中国4,000年の歴史などにも質問・議論が及んだ。 横浜の美産探訪会 6月18日(土) 横浜市内・中華街(参加者17名)。 梅雨の中休み晴天の中、「中華街―ヨコハマの都市形成を歩く」探訪会はみなとみらい線「日本大通り」駅からスタートし、官庁街から水町通り、山下公園、中華街へ。藤嶋さんから中華街の牌楼・関帝廟などの解説の合間に、餃子、ラーメン、お粥などの美味しいお店の紹介があり、中華街に対する参加者の興味をより一層惹きつけた。探訪会の後の交歓会(自由参加)は藤嶋さん一押しの広東料理の「吉兆」で行ない、味とボリュームそして仲間同士の気の置けない交歓を楽しんだ。 |
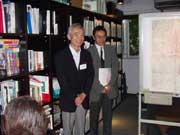 研究会 PA研究所にて
 探訪会 吉田家の内部
|
第23回催事 関西の地域美産会員が企画・案内、京都美産研究・探訪会そのⅠ「京都の町家研究・探訪会」京都の町家研究会 5月25日(水) PA研究所図書室(参加者15名)。 『京の風情を伝える町家、その建物と暮しの美学を吉田家/秦家に尋ねる』と題して、5月25日(水)研究会を東京で田中哲氏(建築家)と杉村が、町家の歴史と建物の特長を京都の歴史を交えて概括。研究会後交歓会(自由参加)が行われ、東京を離れて関西で始めて開催される探訪会への期待の大きさを語り合った。 京都の町家探訪会 5月29日(日)参加者20名。 いま人気の高い京都の町屋探訪会には20名もの参加があり大変盛り上がった。関西の橋本 完氏(アトリエまほろ 主宰)、森山貴之氏(神戸芸工大講師)が町家の優れモノたちを、新町通の吉田家と油小路通の秦家を中心に探訪。吉田家では、当主で文化財保存リーダーの吉田幸次郎さんから同家や町家と祇園祭との深い係わり合いを聞いた。秦家では当主の秦めぐみさんに、奥座敷で最上の町家京料理を当主特選の銘酒で味わった後、「太子堂奇慶丸」として小児薬を商ってきた秦家の歴史・生活などの話があり、その凛とした町家住まいの息遣いを感じた。最後に森山氏が「パリと京都の町並みの比較」、橋本氏が「町家の再生と活用」というテーマで話し、京都の町家探訪会を締めくくった。 |
 説明する岡林さん PA研究所
 参加者も真剣な研究会 PA研究所
|
第22回催事「鎌倉美産研究/探訪会シリーズ」そのⅡ『鎌倉の現代文化を象徴する鎌倉文学館や文士邸を訪ね古の寺社に立寄る』平成17年(2005)4月23日(土)10:00~18:00 鎌倉探訪会 平成17年(2005)4月20日(水)18:00~20:00 鎌倉研究会 第12 回研究会 PA研究所図書室(参加者12名)。鎌倉生まれ鎌倉育ち、銀行マンを卒業後は市民委員として鎌倉市のまちづくりに尽力中の美産会会員岡林馨さん企画の「鎌倉美産研究/探訪会シリーズ」そのⅡ』の事前勉強会が開催された。研究会後交歓会(自由参加)が行われ、岡林さんの優れた研究内容の余韻を楽しんだ。 |
 年度末交歓パ-ティ
 2年間の活動記念講演会
|
平成17(2005)年3月20日(日)17:30~20:00、年度末記念交歓パーティ、東京表参道会員有志の企画・運営による年度末記念交歓パーティ(第1回);表参道沿いレスラン「ベルーガ」。「ベルーガ」は、内装が本格的アールデコの設え(しつら)で有名。房総の自家農場直産の有機栽培食材による特別料理提供。川越、房総佐貫、原宿表参道探訪会など今期(平成16年4月~17年3月)開催の各探訪会と研究会参加者26名が、札幌、高岡、大阪など遠方からも集い、講師や各催事企画案内者と熱い想いを語りあった。 平成17(2005)年3月20日(日)14:00~17:15、PA研究所図書室 記念講演会(第11回研究会);14:00~17:15 PA研究所図書室。地域美産探訪/研究会の「地域美産会2年間の活動を記念して、田村 明さん(名誉会員)と角坂 裕さん(世話人)の記念講演会」 テーマ;(1) 田村 明‥「まちづくりとパブリックアート、そして地域美産」(2) 角坂 裕‥「多摩川の歴史」。戦後日本の都市景観づくりの基を拓いた田村 明さん、多摩川の美産たちをこよなく愛する角坂 裕さんの講演+参加者とのフリートーキング。参加者29名 |
 川越東照宮拝殿、PA研究所撮影
|
平成17(2005)年2月26日(土)10:30~20:00、川越市第20回催事:第14回地域美産探訪会、埼玉県立近代美術館学芸主幹、伊豆井秀一さんが案内する『江戸文化に根ざす、川越市とっておきの美産たち‥そのⅡ<江戸期に建てられた歴史的建造物を訪ねる>探訪会』。川越の経済と文化が頂点に達した江戸期に造られた社や寺院など、川越文化の基礎を形づくる歴史的建造物の学習と探訪です。川越氷川神社、本丸御殿、喜多院、仙波東照宮など、川越ならではの江戸時代の建築美産たちを探訪、当日夕の交歓会は“さつまいも”の専門銘亭「いも膳」で。参加者25名 平成17(2005)年2月23日(木)18:20~20:00 PA研究所図書室 第20回催事:第14回地域美産研究会、埼玉県立近代美術館学芸主幹、伊豆井秀一さんが案内する『江戸文化に根ざす、川越市とっておきの美産たち‥そのⅡ<江戸期に建てられた歴史的建造物を訪ねる>研究会』 参加者14名 |
 探訪会、鈴木喜尚さんの解説
 羽田美産研究会
|
平成17(2005)年1月29日(土)13:20~20:00第19回催事:第13回探訪会・交歓会:素朴朴な社(やしろ)探訪家、角坂裕さんが案内する『私が愛する多摩川水系の素朴な社(やしろ)と美産たち‥そのⅢ<多摩川の河口、羽田猟師町界隈(かいわい)の社(やしろ)と美産>』。羽田神社、大谷政吉佃煮店、羽田の渡跡、赤煉瓦防潮堤、無縁供養堂、弁天橋大鳥居、穴守稲荷神社等を探訪。30代から80代までの男女29名が、地元の美産発掘推進者、鈴木喜尚さんを含めて参加。交歓会は羽田沖の魚料理名店「ゆたか」で、羽田漁協組合長伊東俊次さんの多摩川浄化問題とアナゴ漁のレクチャーをまじえ、地元の肴を堪能。 平成17(2005)年1月27日(木)18:20~21:00 PA研究所図書室 第9回研究会・交歓会:素朴朴な社(やしろ)探訪家、角坂裕さんが案内する『私が愛する多摩川水系の素朴な社(やしろ)と美産たち‥そのⅢ<多摩川の河口、羽田猟師町界隈(かいわい)の社(やしろ)と美産>』の事前勉強会。16名参加。交歓会はセブンシーズで。 |
 平成16年忘年会
 藤嶋PA研究会
|
●平成16(2004)年12月11日(土)18:00~21:00第18回催事:第1回忘年会;表参道「コケコッコ」第8回研究会終了後、今年度忘年会が表参道の焼き鳥店「コケコッコ」で開かれ、14名の参加者が藤嶋俊会さんの昼間の講話を巡る議論の延長や、今期開催した他の探訪会・研究会を巡る話題を肴に愉快に交歓 ●平成16(2004)年12月11日(土)15:00~17:30 第18回催事:第8回研究会、PA研究所図書室;美術評論家、藤嶋俊会の企画・講話「第2回妻有トリエンナーレを見る‥スライドとトーク」。 当会の世話人の一人で、美術評論家かつパブリックアート研究者の藤嶋俊会さんが、ここ数年新潟県中越豪雪地帯の越後妻有地域で行われている北川フラム氏(アートプロデューサー)主導の、アートによる地域おこしイベント「第2回越後妻有トリエンナーレ」の現場を調査して、地域内に制作された作品の質性と環境・景観との整合性、地域の人々の関わり方などについてスライドと文章資料を使いながら講話したあと、現実の地域おこしに参加したパブリックアートの効用と限界などについて、遠くは大阪・富山などから参加した13名の同好者たちと意見を交換。 |
 鶴岡八幡宮二之鳥居前
 鎌倉美産研究会、PA研究所
|
●平成16(2004)年11月27日(土)10時20分~20時第17回催事:第12回探訪会、鎌倉市の市民委員/美産会員、岡林 馨の『源/北条と臨済の美産たちに鎌倉文化の源を訊ねて、座禅の会も体験する』。 ●平成16(2004)年11月24日(水)18時~19時30分 第7回研究会、パブリックアート研究所図書室。鎌倉市の市民委員・美産会員、岡林 馨の「臨済禅と鎌倉・北条の武家文化」。 |
 表参道、撮影PA研究所
 秋葉神社、撮影PA研究所
 探訪会風景、撮影西山郁夫
|
●平成16(2004)年10月16日(土)9時30分~17時:第16回催事、第11回探訪会。パブリックアート研究所代表、杉村荘吉、企画案内、 50数年前の原宿表参道は、明治神宮とその横の米駐留軍キャンプに通じる、人通りの少ない閑静な欅並木通りだったが、現在は日本や外国のブランド店、50 以上が軒を連ねて、年間4百万人(欅会事務局調べ)に及ぶ来街者が訪れる日本で一二を競う商業街区に成長。豊かに茂る大欅のモール(緑道)がつくり出すエレガントでさわやかな景観と、多種多彩なお店が提供する先端的商品とサービスを求めて、国内、アジア、欧米の各国から、ヤングからシニアまで、個人から家族連れまで、あらゆる階層の人々を夫々なりに魅了する、アジアを代表する優雅でトレンディな街に変身。 原宿表参道探訪/研究会‥そのⅠ、探訪会の部は、この探訪/研究会シリーズの入門編と位置付けて、先ずこの街の歴史と今を概観するため、永くこの地の変遷を見続けた地域の鳥居、社、古道など、街のルーツを訪ねながら、今この街を代表する有名ブランド店、先端事業店、再開発事業現場などを訪ねて、経営を担う人々からこの街への想い経営哲学を聞き、街の魅力を肌で味わい学びながら、街の明日を想ってみる内容。参加者は30名で、その中に商店街振興組合「欅会」理事長山本正旺さん他5名の地元関係者が参加。商店街振興組合、原宿表参道欅会の協賛、渋谷区の後援。ランチ:「八竹」の大阪鮨折。交歓会:レストラン「ベルーガ」、房総丘自家農園産の有機野菜を仏料理仕立で。 ●平成16(2004)年10月14日(木)18~20時: 第16回催事・第6回研究会、パブリックアート研究所代表、杉村荘吉、企画講演、原宿表参道の美産探訪/研究会‥そのⅠ(概観編)、研究会の部『原宿表参道に古き美産(鳥居・社・古道)を訪ねて、新しき(先端店や街並づくり)を知る』 どんな商店街(繁栄衰退に係わらず)もそれなりの歴史や文化的背景を持ち、それらが地域の街文化をつくり、その街文化の下で様々な商店街活動が行われている。今日本で最も人を世界中から集めている街、原宿表参道。この街の歴史と現在の事業が産み出す良きモノたちの審美性を、アートのモノサシを使って評価。参加者15名。 |
 川越市立博物館での解説
 伊豆井さんの解説
|
●平成16年6月19日(土)10:15~17時:第15回催事・第10回探訪会 埼玉県立近代美術館学芸主幹、伊豆井秀一、企画案内、「江戸文化に根ざす、川越市とっておきの美産たち‥その1-2」 埼玉県立近代美術館学芸主幹ならではの豊富な地元情報をもとに、伊豆井秀一さんが企画案内した2月28日の「江戸文化に根ざす、とっておきの川越美産たち探訪会」のアンコール編「その1-2」は、コースも先回とほぼ同じ内容の、川越市立博物館→養寿院→蔵造りの町並み→旧武州銀行→山崎家別邸→日本聖公会川越教会→大正ロマン通り、で開催。久ぶりの晴天の下、川越市立博物館で同市文化財保護課、加藤忠正さんから川越街文化の歴史解説を聞いた後、伊豆井さん選りすぐりの川越美産を同氏の解説付で探訪。 昼食は、川越きっての洋食老舗、太陽軒での特別メニューのランチ。交歓会は文化5年創業のうなぎ老舗「小川菊」で行い、この日探訪した美産たちや街づくりの印象などを素直に述べ合った。 その際、蔵の街並み通りで芋せんべい店「芋元」を営む関口 汎さんから、「川越市の蔵の街並み保存条例の制定に従って店舗住宅の改造に応じて商売を続けているが、観光客数の増大が商売に結びつかずジリ貧状態の中でこれからの生活をどう立て直そうか思案中。そうゆう例が一杯あることも外部の人に知って欲しい」という電話を受けたことも事務局から披露。参加者30名。 |
 房総佐貫城大手門址
 宮 醤油店
 佐貫研究会
|
●平成16年5月20日(木)11時~17時:第14回催事・第9回探訪会 パブリックアート研究所代表、杉村荘吉の企画と案内。 佐貫美産探訪会は、「何も魅力的なモノが見えない一見平凡な地方の町も、ちょっと視点を変えて詳しく眺めてみると、素晴らしい美産たちが目に飛び込んでくることを肌で体験する。 それらを『地域の魅力づくり・まちおこし』に生かす可能性をさぐりながら、その成果を地域のリーダーや行政関係者にフィードバックする」を狙って、従来の探訪会の枠を超える実験的企画として開催。 当日は小雨混じりの平日にもかかわらず、一般市民から地域のリーダー(元市会議員など)や産業人(有名ホテル総支配人など)まで25名が参加。杉村荘吉PA 研究所代表の総括解説のもとに、茂木菊夫(佐貫城址遺産保存会)氏が旧ご城下を、宮 正蔵(醤油銘蔵主)氏が、継続家業が創りだした事業美産を案内・解説。 尚、昼食は東京湾観音会館で佐貫名物の「秤目(アナゴ)丼」、交歓会では久留里の銘酒と土地料理、老技による木更津甚句を楽しむ。 数日後、“地域の歴史を生き抜いて家業継続に頑張っている「事業美産」たちに美術館のアートと違ったすごさに感動した”、“当日もらった解説資料を改めて読み直して、まちおこしを有志たちで真剣に考えみることにした”等、参加者多数から熱い感想が寄せられた。 ●平成16年5月18日(火)15時~17時: 第13回催事・第5回研究会 「パブリックアートと地域美産、房総佐貫に江戸から続く手造り醤油銘蔵と旧ご城下跡を訪ねて、地域の美産を味わい街おこしを考える」パブリックアート研究所代表、杉村荘吉。 「何も魅力的なモノが見えない一見平凡な地方の町も、ちょっと視点を変えて詳しく眺めてみると、素晴らしい美産たちが目に飛び込んでくることを肌で体験する。 それらを『地域の魅力づくり・まちおこし』に生かす可能性をさぐりながら、その成果を地域のリーダーや行政関係者にフィードバックする」を主旨に、2日後(20日木)に開催する探訪会のための事前勉強会として開催。 パブリックアートから社会美産、そして地域美産への流れも解説。 参加者数:2催事で25名 |
 地下鉄大江戸線PA探訪会
 地下鉄大江戸線PA研究会
|
● 平成16年4月25日(日):11時~17時第12回催事・第8回特選探訪会:「地下鉄大江戸線のパブリックアートと駅デザイン」 地下鉄大江戸線環状部13駅 東京地下鉄建設(株)総務本部専任副本部長、石村誠人さんにとって同社在職最後の見学会となった「地下鉄大江戸線のパブリックアートと駅デザイン」探訪会は、10時50分に東新宿駅に集合後、石村さん厳選の同環状線13駅に施工された駅デザインとパブリックアートの優れモノたちを、同氏の実施体験に裏付けされた知識と情報を入れ込んだ解説で見学した。当日は大阪や富山から駆けつけたパブリックアートの専門家に、シニア市民、主婦、公共団体職員、ボランティア勤務者などに、世界の地下鉄文化を探訪中の米人女性が加わった11名が、語学交流も楽しみながら、地下鉄大江戸環状線各駅の美産たちを観賞・評価して歩いた。それらの美産たちの中では、特に飯田橋駅の排気塔にアートを演出したfunctional artwork に参加者の注目が集まった。 参加料:会員1,500円/非会員3,500円(地下鉄乗車券、ランチ、交歓会自己負担) 参加者:11名 ● 平成16年4月23日(金):15時~17時:PA研究所図書室 第11回催事・第4回研究会:「地下鉄大江戸線環状部のパブリックアートと駅デザイン‥その企画づくりから竣工開通まで、そして開通後60回にも及ぶ見学ツアー案内などの実践活動で見えたもの」 石村誠人さんは、5年前に日本開発銀行から東京地下鉄建設(株)へ出向したことから、地下鉄大江戸線環状部のパブリックアートと駅デザインの企画づくりから竣工開通まで、総務本部専任副本部長として同事業の調整、遂行監理を行ってきた人で、今月末同社を退社しました。 今回の第4回研究会は、「地下鉄大江戸線環状部のパブリックアートと駅デザイン、その企画づくりから竣工開通まで、そして開通後60回にも及ぶ見学ツアー案内などの実践活動で見えたもの」を、公開資料・オフレコ話など多彩な資料・情報をまじえて語った。参加人数は6名と少人数だったが大阪から参加した会員もおり、少数ゆえに付近のレストラン(セブンシーズ)で開かれた交歓会での話も含めて大変実りのある研究会となりました。 尚、この会から第2年度(平成16年4月~平成17年3月)の活動開始。 参加費:会員1,000円/非会員2,500円(探訪会参加者は無料) 参加者:6名 |
 川越市蔵造りを解説
|
● 平成16年2月28日(土):11時~17時第10回催事;第7回探訪会「江戸文化に根ざす、川越市とっておきの美産たち」。 参加者:伊豆井秀一を含む世話人5名、会員6名、一般参加23名、その他3名(読売記者2名、川越市文化財保護課1名)計3名 |
 PA研究所図書室出の英語懇談会
|
● 平成16年2月24日(火):11時~14時第9回:第3回セミナー懇談会; 日本の伝統的美産研究家、バーバラ・サンドリッセ(米国人)さん東京立寄りに際して、会員/参加者との特別交流懇談会、『日本の魅力的な美産たち‥そのⅢ』を、PA研究室図書室+昼食会で開催。 平成13年9月明治神宮文化館で開催の「都心の鳥居を訪ね、話を聞き、語り合う会」で、私たちに日本の美産の審美性を独自の視点で語ったバーバラ・サンドリッセさん。昨年4月の来日に際したトーク会では、日本の桜の魅力を語り参加者を魅了しましたが、今回の来日では、女史が今一番惹かれている日本の美産について、特別懇談会へ出席する人々とやさしい英語で語り合い、昼食会をまじえて懇談する趣向。 懇談会場:パブリックアート研究所図書室。 昼食交流会:南青山、やんも |
 見学会風景 提供 PA研究所
|
● 平成15年12月21日(日)11時~17時第7回催事:第6回 特別探訪会「地下鉄大江戸線のパブリックアートを無料見学する」 コース:東新宿→牛込神楽坂駅→飯田橋駅→勝どき橋駅(昼食)休憩約60分→汐留駅→大門駅→赤羽橋駅→六本木駅→国立競技場→代々木駅。 |
 横浜探訪会Ⅲ鉄道道、撮影廣瀬道孝
|
● 平成15年11月15日(土)12時~夕第6回催事:第5回 探訪会、神奈川県民ホールギャラリー課長、藤嶋俊会さん企画・案内する 昼食かねた事前解説の後、汽車道→赤レンガ倉庫→ドッグヤード→岩亀稲荷→掃部山公園→県立音楽堂→伊勢山皇太神宮→美空ひばり像と探訪し、夕方「小半(こなら)」で交歓会。 |
 狛江百塚古墳 提供 PA研究所
|
● 平成15(2003)年10月15日(土)午後第6回催事:第4回探訪会、素朴な社(やしろ)探訪家、角坂 裕さんが案内する「私が愛する多摩川水系の素朴な社(やしろ)と美産たち‥そのⅡ、東京都狛江市の内外に点在する美産たち」を訪ねた。 |
 撮影 PA研究所
|
● 平成15(2003)年5月10日(土)午後第5回:第3回探訪会、神奈川県民ホールギャラリー課長、藤嶋俊会さんが案内する、横浜の地域美産を尋(たず)ねるPARTⅡ『モダン都市の異国情緒を歩く-元町・山手・山下公園-』、お菓子屋や家具屋が並ぶ元町、外人墓地、西洋館、教会、ミッションスクール、港が見える丘公園、山下公園‥日本の近代化遺産を尋(たず)ねた後、横浜を象徴するドイツレストラン「アルテリーベ」で交歓会。同探訪会、産經新聞が取材し5月11日(日)朝刊に同行記事を掲載。 |
 撮影 PA研究所
|
● 平成15(2003)年4月19日(土)午後第4回:第2回探訪会『私が愛する多摩川水系の素朴な社(やしろ)と美産たち1‥玉川上水羽村堰(せき)』素朴な社(やしろ)の探訪家で建築家の角坂 裕さんが選んだ心惹かれる美産たちを、地元の協力(西暦700年頃創建された阿蘇神社での神酒頂戴と解説、郷土博物館学芸員の解説など)を得て角坂さんの案内で探訪し、地元名舗の川魚料理や地酒を含めて賞味堪能しました。 |
 撮影 PA研究所
|
● 平成15(2003)年4月15日(火)夕第3回:第2回セミナー、米国人鳥居研究家、バーバラ・サンドリッセさん再来日記念特別トーク、『私を魅了してやまない日本の美産たち』・PA研究室、図書室。平成13年9月開催の「都心の鳥居を訪ね、話を聞き、語り合う会」レクチャーで私たちに大きな衝撃を残したバーバラ・サンドリッセさんが再び来日、日本の桜の魅力をこの日のために用意した図版と写真を紹介しながら解説して、またまた参加者を魅了しました。 |
 撮影 PA研究所
|
● 平成15(2003)年3月28日(金)夕第2回:第1回セミナー、第1回パブリックアート研究会;『パブリックアートの効用、地域再生と生涯教育活動から報告』 PA研究所図書室。富山大学教育学部教授・彫刻家、長谷川総一郎さんが、仲間たちと一緒に過去10年間、富山県下の地域再生と生涯教育の現場で実践したパブリックアート活動を報告し、それを巡ってさまざまな質問と意見が飛び交(か)いました。 |
 撮影 PA研究所
|
● 平成14(2003)年12月7日(土)午後第1回:第1回探訪会:『横浜市中心街の地域美産いろいろ‥その1』;:第1回美産探訪会は、神奈川県民ホールギャラリー課長、藤嶋俊会さんが企画・案内する『横浜市中心街の地域美産いろいろ‥その1』。雨まじりの寒い日にもかかわらず、学生、主婦、シニア市民、アート研究者など多彩な人々が札幌など遠隔地からも集まり、講師の解説で関内を代表する美産たちを訪ねたのち、文明開化の明治初期開店の老舗、「太田なわのれん」の牛鍋を味わいました。 |